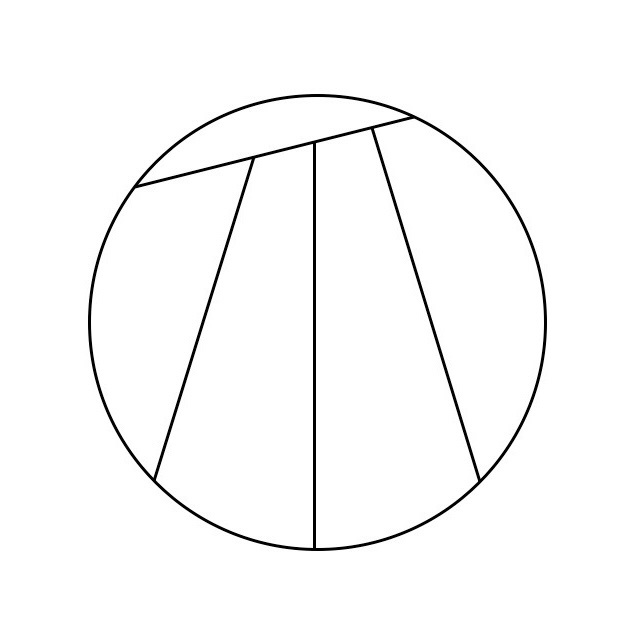高尚な音楽と思われがちなクラシック音楽だけれど、本来はポップスやロックと同じで誰もが楽しめる懐の広い音楽だったはず。この連載では、写真家・大森克己が案内人となり、クラシック音楽にこれから触れようと思っている人のために音楽評論とは違った視点でクラシック音楽を解説。第二回目はルネサンス時代に流行したポリフォニーと呼ばれる無伴奏合唱曲を紹介する。
”500年前のボンジュール “
偏愛「クラシック」案内と銘打ちながら、今回紹介する音楽は、ひょっとしたら「クラシック」と呼ばれることは少ないのかもしれない。普通、西洋のクラシック音楽といえば17世紀から18世紀に活躍したバッハ以降、モーツァルトやベートーヴェンなどの古典派、ショパンなどのロマン派を経て20世紀初頭のマーラーあたりまでの作曲家による音楽を指す場合が多い。しかし、ちょっと考えてみれば分かることだがバッハ以前にも数多の音楽は存在した訳で、そのなかでも15世紀から16世紀はポリフォニーと呼ばれる美しい無伴奏の合唱曲の最盛期でもあった。いまから500年近く前のルネサンスの時代、日本でいうところの室町後期から安土桃山時代の頃のヨーロッパの声である。

その頃の職業作曲家の仕事の中心は神に捧げるための音楽であり、いわゆる宗教曲、ミサ曲というものの中に数々の美しい傑作がある。しかし、恋愛や諍いや酒などの世俗的な歌詞を歌った音楽にも、驚くほど21世紀に生きる人間の心に響いて来るものがあって、ボクが初めて聴いてノックアウトされたのはオルランドゥス・ラッスス(Orlandus Lassus)というフランドル(現在のベルギー、オランダ、フランスにまたがる地域)の作曲家の「Bonjour mon Coeur」というシャンソンだった。
https://open.spotify.com/track/3hF0jkGMGU3xv5OYIlOMU0?si=PlhJsPupRMC1Ecl7DUGU6g
初めて何かに出会うことの喜びが感じられるハーモニー。「ボンジュール(こんにちは)」というごく普通の日常のあいさつのことばがが、こんなにもみずみずしく感じられることにうれしくなる。ピエール・ド・ロンサール ( Pierre de Ronsard )という詩人による歌詞も素晴らしい。
Bonjour mon coeur, bonjour ma douce vie.
Bonjour mon oeil, bonjour ma chère amie,
Hé ! bonjour ma toute belle,
Ma mignardise, bonjour,
Mes délices, mon amour,
Mon doux printemps, ma douce fleur nouvelle,
Mon doux plaisir, ma douce colombelle,
Mon passereau, ma gente tourterelle,
Bonjour, ma douce rebelle.
(Pierre de Ronsard)
---こんにちは、私のハート、私の甘い生命。私の目、私の親愛なる友よ、あぁ、私のとびきりの美しい人よ、私の可愛いひとよ、私の優しい春、私の可愛い初々しい花、私の甘い喜び、私の恋人、私の可愛い小鳩、私の雀、私の美しいきじ鳩、こんにちは、私の優しい反乱者よ---(「Bonjour mon couer 」詩:ピエール・ド・ロンサール)
人間の声というのはそもそも最も原始的な楽器であって、徒手空拳で何の道具も楽器も使うことなくメロディーとリズムを作り出し、新しい時空間を立ち上げることができる。その不思議さと凄みが、こんなにもお洒落にサラッと表現されていることにびっくりする。写真家である自分は「こんにちは、私の目」というフレーズにグッと来ると同時に「優しい反乱者」っていうのが一体どういう存在なのか、聴く度にドキドキしながら想像する。

さて、ルネサンスのポリフォニーの作曲家の中で最も有名な一人、ジョスカン・デ・プレ(Josquin Des Prez)という人の曲も是非聴いていただきたい。複数の旋律が互いに追いかけあいながら絡みあい、えもいわれず美しく響く。こんなにも洗練された表現が500年以上も前に存在していたことに驚いてしまう。
https://open.spotify.com/track/3fzZWwKHUVdKwcaO9Ofj3H?si=4a2WWMu1QlOwzpjBLyHrBQ
これは「わが子アブサロン(Absalon fili mi)」というモテット(ミサ曲ではない短い宗教曲)。1497年の教皇アレクサンデル6世の息子の死、または1506年の皇帝マクシミリアン1世の息子の死を悼んで作られたという喪の歌である。親しい人を亡くした人間の嘆きや悲しみと怖れ。世界中で戦争や紛争、災害が絶えることなく、亡くなっていく人も後をたたないことを意識せざるを得ない2024年の現在にふさわしい音楽、遠い過去からのメッセージになりうるかもしれない。

https://open.spotify.com/track/1obsUrLzPohrHDb4Bn6R1U?si=9mTYihq1QfqPMB8l004qLw
最後の曲は16世紀にイタリアで栄えたマドリガーレという形式の音楽から。ナポリ近郊のヴェノーザで生まれ、エミリア=ロマーニャのフェッラーラを中心に活躍したカルロ・ジェズアルド(Carlo Gesualdo )の「ああ、苦しみのなかで息絶えよう(Moro, lasso, al mio duolo )」
随所に登場する半音階と不協和音、官能的な歌詞、子音の響きがあいまって愛のダークサイドを強く感じさせる音楽である。なんだか矛盾した言い方かもしれないが、暗い快楽、退廃という豊かさ。触り、触られ、囁きあいながら奈落に落ちる時間の生きている実感。実際にジェズアルドは妻の不倫現場に踏み込んで、妻とその相手を殺してしまった、という人でもあった。そのことが彼の音楽制作にどの程度の影響を及ぼしたのかは知る由もないが、一人で深夜にヘッドフォンで聴く、ということはあまりお薦めできない音楽かもしれない。人間と人間がナマでぶつかり合う時に起こる化学反応の複雑さを体感して噛み締めたい。

ここで紹介した500年前の音楽は、ボク達の耳に馴染みのあるロマン派以降の音楽とは、かなり違った音の響き方をする。特に和音、和声の美しさは得もいわれぬものだ。そして拍の感覚、リズム、時間の流れ方もまったく違う。その理由を真面目に話すと長くなってしまうので割愛するけれど、時間を逆算しているみたいな乱暴な言い方をあえてしてみると、ターンテーブルの無いヒップホップ、シンセサイザーの無いテクノ、エレキギターの無いロックンロール、そんなものを想像するのが難しいように、ルネサンスやバロックの音楽(器楽曲も含めて)っていうのは、ピアノの存在しない時代のクラシック、ともいえるかもしれない。音楽のあり方、表現というのはテクノロジーと密接な関係があって、さまざまな現代的な機器が無かった時代に人間はどのように音と向き合っていたのか、自然とどんな風に共存していたのか興味はつきない。
(1オクターブを均等に12分割する平均律という考え方とピアノの発明っていうのは音楽史にとって、めちゃ重要な事件なので、興味のある方はググってみてください)